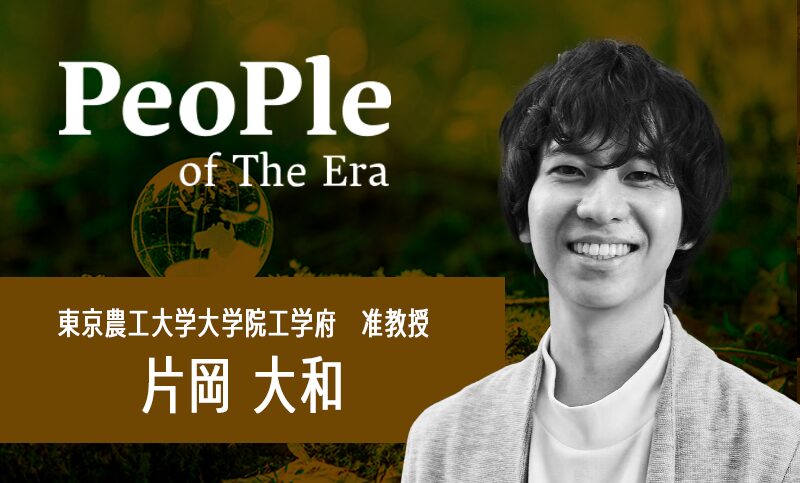インタビュー取材にご協力いただいた方
片岡 大和(かたおか やまと)氏 東京農工大学大学院工学府・准教授
早稲田大学教育学部国語国文学科卒業後、Portland State University LOHAS修了。P&Gジャパン株式会社、P&Gイノベーション合同会社、Procter & Gamble International Operations(シンガポール)を経て、2020年に株式会社Marketing Sub Domainの代表取締役CEOに就任。株式会社TRULYの社外取締役を歴任、natural tech株式会社の取締役COOを現任し、2024年より現職。
海外進出する場合、優れた技術だけではなくマーケティングや戦略的思考が必要になりました。とくにスタートアップのグローバル展開においては、日本と同様な考えを海外に持ち込むと、失敗する確率が高くなります。
MOTとは何か、なぜ日本はグローバルな視点が欠けてしまうのか、海外投資家やベンチャーキャピタルからの支援を得るにはどのようにすべきか。そこで今回、スタートアップのグローバル戦略論に取り組まれてきた東京農工大学大学院工学府の片岡 大和先生にお話を伺いました。
「いいものを作れば売れる」という時代が終わり、MOTが必要に
―― MOT(Management of Technology)とは?
片岡先生:MOTとは、技術を経営に活かすための考え方で、1990年代にアメリカで提唱されたのが発祥と言われています。現代においては、消費者の求める商品やサービスを企画するためには、優れた技術だけではなくマーケティングや戦略的思考も重要なんですね。社会のニーズがモノやサービスの単なる機能的価値から、意味的・情緒的価値へと転換しました。
MBAが経営一般を専門的に学ぶのに対し、MOTは開発分野の先験的な知見やノウハウを活かしながら、経営やマーケティング、知財について学びます。製造業やサービス業の新規事業開発の実現を支援することを目的としているのがMOTです。
―― なぜMOTが注目されるようになったのでしょうか?
片岡先生:日本では「いいものを作れば売れる」という時代が長く続いたため、優秀な理系の学生は研究者になり、優秀な文系の学生は花形の営業職として活躍していたのです。そこにはマーケティングや戦略的視点が不足した状態でした。しかし、モノがあふれている現代では、いいものを作っても売れないですよね。そのため、「裏側に消費者や購買者にどんな悩みがあるのか」「どんな課題解決をしてくれるのか」についての視点が必要になってきました。そのような意味で、MOTが最近注目されるようになったのではないかと思います。
日本固有の企業文化の弊害とマーケティングに対する理解不足
―― そもそも日本はこうしたMOTが苦手なのでしょうか? また苦手だとしたらなぜ苦手なのでしょうか?
片岡先生:私が知っている限りにおいては、2つの理由が考えられます。1つ目は、日本の終身雇用制度や総合職採用の文化が影響しているからです。終身雇用制度では、別に目の前の結果に責任を追わなくても、とりあえず若いときにがむしゃらに働き、年功序列で高い給料がもらえるのが当たり前で、MOTのような発想もしくは経営的な発想をしなくても、済んでいたのです。また総合職採用では、ジョブローテーションが前提のため、専門性が身につきにくいというデメリットもあります。
2つ目は、高度経済成長期の成功体験により、「いいものを作れば売れる」という考え方が根強く残り、マーケティングやブランディングの重要性が理解されにくいことです。とくに、いくつかの大企業では、マーケティングを「邪道」と捉える風潮がいまだに残っています。先ほども申し上げたように、理系だったら研究開発、文系だったら営業と決まっているので、マーケティング人材も不足しています。
―― マーケティング人材が不足している現状について教えてください
片岡先生:マーケティングという言葉が一人歩きしてしまっている現状があります。マーケティングと一口に言っても、実際はかなり細分化されています。デジタルマーケティングはインターネットやIT技術を用いたマーケティング手法ですし、ブランドマーケティングとはブランドの基本設計、関係者の意思統一、具体的な施策立案と実行、成果測定を行うマーケティング手法です。リテールマーケティングはイオンやマツモトキヨシのような小売店の売場に商品が並ぶことが重要という考え方から、小売業の売場起点で行うマーケティング手法をいいます。近年ではB to B to C事業ではトレードマーケティングという職種も出始めていますね。このようにマーケティングも多種多様ですが、日本ではこれらが一括りにされ、適切な活用がなされていないことが課題ですね。
―― マーケティングの観点から見て、なぜ日本はグローバルな視点が欠けてしまうのでしょうか?
片岡先生:グローバルな視点が欠けてしまう要因として、言語的な障壁と国内市場の大きさが挙げられます。米国合衆国国務省が公表した、「言語習得難易度ランク(Language Learning Difficulty for English Speakers)」があります。このランキングは英語を話す母語話者がそれ以外の言語を学ぶときにどれぐらい苦労するかをリスト化しているのですが、日本語は韓国語や中国語と並び、5段階のカテゴリーの5番目です。つまり、逆から見ても日本人が英語を学ぶのが難しいことが分かります。日本人がサボっているわけではなく、単純に言語的隔たりが大きいので、英語の習得は簡単ではありません。
国内市場規模の面で言うと、2015年のデータでは、日本の東京証券取引所は世界第3位です。東京だけではなく、札幌や名古屋、福岡にも証券取引所があるので、比較的小型上場しやすい環境が整っているんですね。こうしたことが要因となって、わざわざ一攫千金で海外を狙う必要がなかったのではないかと思っています。例えば証券取引所がない国だったら、海外で上場する必要があるため、無理やり海外に行くでしょう。あるいは、小さな証券取引所しかなければ海外の市場を目指すかもしれません。
マーケットの環境を正しく理解するためにネイティブ人材の採用が必須
―― MOTの視点からグローバル展開するスタートアップに必要なことはどのようなことでしょうか?
片岡先生:スタートアップに必要な要素には、3つのポイントがあります。1つ目は、マーケット環境の正しい理解です。3C分析を使って顧客・競合・自社について把握します。海外は文化も風習も異なり、物価も違いますし、競合の数も10~20倍です。とくに顧客と競合の分析が重要ですが、スタートアップはリソースが限られています。選択と集中を適切に行うためには市場調査が欠かせません。
2つ目は、プロダクトの優位性を保つことです。競合との差別化を明確にし、なぜその商品が選ばれるのかを意識することが必要になります。「POD(ポイント・オブ・ディファレンス)」と呼ばれる「差別化ポイント」を作っておくことが重要です。
3つ目は組織構成を考えることです。スタートアップは少人数で始まることが多いのですが、早い段階で役割分担や意思決定のプロセスを明確にすることが成功の鍵となります。よくあるスタートアップの失敗事例は役員同士が揉めることです。役割分担を明確にし、システム導入はCTO、マーケティングや採用の最終意思決定者はCOO、ファイナンスの最終意思決定者はCEOといったように、分野ごとの意思決定者を決めるのがいいでしょう。
―― グローバル展開を考える際、とくに意識すべき点はどのようなことでしょうか?
片岡先生:先ほども申し上げたように、スタートアップに関して言うと、マーケットの環境を正しく理解し、プロダクトの優位性を保つことが重要です。グローバルで勝ち抜くには「Why Japan?」を徹底的に考えることが「Thought-starter question」だと思っています。「Thought-starter question」とは、思考のスイッチを入れる質問を指します。少子高齢化、資源が少ない、食品、エンタメ、ロボットなどが日本の優位性を保てる領域です。ただし、あくまでもプロダクト上の問題であって、日本人が立ち上げた会社であることは何の強みにもなりません。
組織構成の面に関しては、言語や文化の壁が生まれやすいので、中長期的な採用メリットも考えて、早めにネイティブ人材を採用すべきだと思います。ネイティブ人材は単に言語が話せる人間ではなくて、文化や風習をきちんと理解しているメンバーであることが重要です。優秀な外国人コミュニティを囲うこともできますし、仲間を呼んでもらって採用することもできます。さらに、その社員が子会社の社長になって、海外の子会社を拡大してくれたら、一層、規模を拡大できるでしょう。海外のスタートアップではPh.D.を持つCEOとMBAを持つCOOなど、役員間での強みが明確であることが多いですね。
―― グローバル展開での失敗例について教えてください
片岡先生:日系企業、とくに大企業においては、日本での成功事例をそのまま海外に横展開して失敗するケースが目立ちます。白物家電は日本企業の代表的な失敗例です。日本では白物家電がヒットし、洗濯と言えば白いものを想像しますし、冷蔵庫も白いものが売れて、洗濯機に関しては機能が多ければ多いほどいいとされています。そこで、ある企業は中国でもフィリピンでも、多機能の白物家電をそのまま持っていきました。中国は、黄砂によってすぐ汚れるので、白い家電が好まれません。その結果、中国での販売は失敗に終わりました。その頃は灰色の家電が好まれていましたが、今では当時と変わり、白黒が好まれています。
また、フィリピンでも日本と同様な家電を販売し、失敗しています。当時のタイやフィリピンのようなアジア圏は、識字率が低いので、多機能のボタンは嫌われたのです。シンプルに「スタートボタン」と「ストップボタン」だけを付けることが必須でした。
化粧品関係の会社も日本で成功した定期販売モデルを中国やシンガポール、台湾でも扱い、失敗しました。実は現地では、定期販売モデルよりも大容量パック購入モデルが好まれます。私たち日本人が当たり前だと思っていることが、海外では当たり前ではありません。ネイティブ人材を採用し、彼らに「どんな人にどういうプロダクトをどのように売るのがいいか」を一緒に考えてもらうことが重要です。
海外投資家やVCの支援を得るには、学歴とピッチ資料の質が重要
―― スタートアップが事業を展開するうえで、「技術の優位性」と「市場適応性」のバランスをどのように考えるべきでしょうか?
片岡先生:事業によっても異なるとは思います。例えば、ある程度コモディティ化している商品の業界であれば競争が激しく、競合との差別化が重要なため、市場適応性を優先すべきでしょう。一方、まだ黎明期の業界の場合、いいものを作れば売れる可能性が高いので、技術優位でいくべきだと思います。
―― とくに技術優位のスタートアップには必要だと思いますが、海外投資家やベンチャーキャピタルからの支援を得るにはどのようにすべきでしょうか?
片岡先生:海外展開を目指す場合、海外の投資家やベンチャーキャピタル(VC)からの支援を得ることが重要です。その際、最も大切なのは「信用」であり、どの投資家から資金を調達するかが大きく影響します。単に資金を提供してくれる相手を選ぶのではなく、企業の成長戦略や背景をしっかりと考慮した上で調達先を決定する必要があります。日本で当たり前にある「信用」が海外に行った途端に一気になくなることは、よくあることです。例えば、日本に本社がある企業が海外に出ても信用されません。一部のVCは、出資する条件に、米国内における本社や支社の設立を求めるケースがあります。
また、海外の投資家は創業役員の学歴を重視することも多く、Ph.D.やMBAの取得や生い立ちが信用に直結します。日本は学歴社会だと揶揄されることも多いですが、海外の方がその傾向がより強いため、学歴や生い立ちが投資判断に影響を与えることを理解しておくべきでしょう。
カリフォルニア州マウンテンビューのシードアクセラレーターである「Yコンビネーター」が有名ですが、同社から出資を受けているだけで、何十億と資金が集まるため、みんな必死に出資をもらえるように頑張るようです。
―― 海外で支援を受けるにあたり、有益な方法があれば教えてください
片岡先生:投資家に支援してもらうには、ピッチ資料の質を向上させることが重要です。ピッチ資料とは、投資家などに自社やサービスを紹介するための短いプレゼンテーションを指します。私自身、ピッチの審査員をさせていただくことがありますが、よくある間違いは、「起業家が伝えたいことを伝えようとする」ことです。起業家が伝えたいことと、投資家が聞きたいことはイコールではありません。ですから、「投資家が知りたいこと」をきちんと伝えることが非常に重要です。
とくに英語など母語でないピッチでは、短時間で投資家の関心を引くことが重要であり、3〜5分間のプレゼンでいかに魅力を伝えるかが鍵となります。そのため、ピッチ資料のキースライドには、将来的なリターンの見込みや、起業家だけが知っていて、投資家が知らない独自の市場情報を盛り込むことが効果的です。たとえば、海外市場での需要が高く、年収が2000万円を超えるケースがあるにもかかわらず、労働者の供給が追いついていない業界情報などは、投資家にとって新たなビジネスチャンスとして魅力的に映ります。そのように起業家だけが知っている情報があるスライドは、ピッチが通りやすくなります。
技術だけではなく、マーケティングによってブランディング戦略をしていく
―― 日本発のスタートアップで、グローバルに成功した事例にはどのようなものがありますか?
片岡先生:日本発のスタートアップでグローバルに成功した事例として、私が注目しているのは、サグリとシンクモフです。シンクモフは大阪万博にも出展する予定のようです。サグリは人工衛星を活用して土地の栄養状態や日照時間を分析し、農業の効率化を支援する事業を展開しています。シンクモフは空気中からだけではなく大気中や排ガス中等からの特定の成分を取り除く多孔性物質「MOF(モフ)」を開発しました。MOFを活用することで、二酸化炭素を回収して炭酸飲料の製造に役立てたり、残量も分かるIoTガスボンベを製造したりするなど、環境問題の解決にも貢献しています。
スタートアップではありませんが、ユニクロを展開しているファーストリテイリングもグローバルに成功している例ですね。ファーストリテイリングの優れているポイントは3つあります。1つ目は組織構造が完成されていて、どの店舗に行っても、きちんとオペレーションがされていることです。2つ目は、フリースに選択と集中を行い、完全にフリースに投資をして、毎年売れ筋商品を出していることです。いろいろな種類の衣服を作っていますが、その中でも看板商品が明確で、選択と集中ができていることが分かります。3つ目は、製造が優れているだけではなく、マーケティングやブランディングがきちんと行われていることです。ユニクロ以外ではソニーやアサヒ飲料・アサヒグループ食品などもグローバル展開で成功している事例ですね。
このように、グローバルで成功するには、技術だけではなくて、マーケティングによってブランディング戦略をしていくことが大事だと思っています。しかし、マーケットをきちんと理解せずに、日本で売れているプロダクトを無理やり海外に当てはめて販売すると、失敗につながりやすいでしょう。
―― 最後に読者の方に向けてメッセージをお願いできますか?
片岡先生:以前、会社で働きながら大学院で、私の講義を受講してくれていた学生がいました。後日、その会社の上長の方から嬉しいFBをいただきました。最初はあまり期待をしていなかったそうですが、大学院で学んだことにより、マーケティング的な発想ができたり、経営者視点が芽生えたりしたそうです。また、マーケティングを学んだことで、ある有名企業に採用になった学生もいます。その学生は最終面接で社長から「本当に受けてくれてありがとう、君みたいな子を求めていたんだ」と言われて握手されたそうです。マーケティングは今後、起業や就職する上でも必ず役に立つ学問だと思っています。MOTやマーケティングに少しでも興味がある方は、ぜひ1回私の講義に遊びにいらしてください。また起業されている方、もしくは会社勤めで、マーケティングについて悩んでいる方がいらっしゃったら、いつでもご連絡いただければと思います。
片岡 大和先生のご紹介リンク:
– 片岡 大和 | 東京農工大学 教員紹介 / Kataoka.Lab