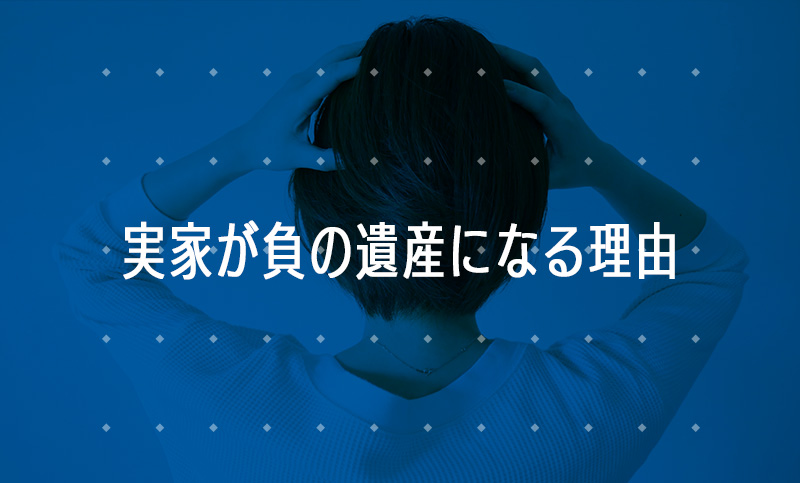皆さんは「実家を相続する」と聞いて、どんなイメージを持ちますか?多くの人は「資産が増える」と考えるかもしれません。しかし現実には、相続した実家が重い負担となるケースが急増しています。総務省の調査によれば、日本の空き家数は約900万戸を超え、住宅全体の約13.8%を占めるまでになりました。
特に地方では、親が住んでいた家を相続したものの、誰も住まず、売ることもできず、維持費だけがかさむ「負動産」となってしまうケースが後を絶ちません。今回は、将来皆さんが直面するかもしれない空き家問題について、その実態と対策を分かりやすく解説します。
なぜ実家が負の遺産になるのか

空き家を持つことの本当のコスト
実家を相続すると、たとえ誰も住んでいなくても様々な費用が発生します。固定資産税(※土地や建物の所有者が毎年支払う税金)は毎年必ず納めなければなりませんし、建物の老朽化を防ぐための修繕費、庭の草刈り費用なども必要です。
空き家を所有することで発生する主な費用は以下の通りです。
- 固定資産税・都市計画税: 年間15万円〜25万円程度(物件により異なる)
- 火災保険料: 年間1万円〜5万円程度
- 維持管理費: 草刈り、清掃、修繕などで年間10万円〜15万円程度
- 光熱費: 最低限の契約でも年間約3万円
一般的に、標準的な一戸建て空き家の維持費は年間35万円から50万円程度かかるとされています。10年間放置すれば、350万円から500万円もの出費となる計算です。
<空き家の年間維持費用の内訳の例>
| 費用項目 | 内訳 | 年間金額 |
|---|---|---|
| 固定資産税(建物) | 1,000万×1.4% | 11.2万円 |
| 固定資産税(土地) | 1,500万×1.4%×1/6 (小規模住宅用地適用) | 3.5万円 |
| 都市計画税(建物) | 1,000万×0.3% | 2.4万円 |
| 都市計画税(土地) | 1,500万×0.3% | 4.5万円 |
| 光熱水費 | 2,500×12カ月 | 3万円 |
| 保険料(火災保険) | 年額 | 3万円 |
| 定期的な庭のメンテナンス費用 | 除草+剪定の概算 | 10万円 |
| 修繕費用 | 概算 | 10万円 |
| 管理費用 | 7,500×12カ月 | 3万円 |
| 交通費 | 3,000×12カ月 | 3万6,000円 |
| 不法投棄された場合のごみ処分費用 | 概算 | 5万円 |
| 合計 | 65.2万円 |
この表を見ると、税金だけでも年間20万円以上かかることが分かります。さらに、建物の老朽化が進めば、屋根や外壁の修繕で一度に40万円以上の費用が発生することもあるのです。
「特定空き家」に指定されるリスク
さらに深刻なのが、2015年に施行された「空家等対策特別措置法」の存在です。適切に管理されていない空き家は「特定空き家」に指定される可能性があります。指定されると、固定資産税の優遇措置(※住宅用地の場合、税額が最大6分の1に軽減される制度)が適用されなくなり、税負担が最大で6倍に跳ね上がることもあるのです。
空き家問題の現状を数字で見る
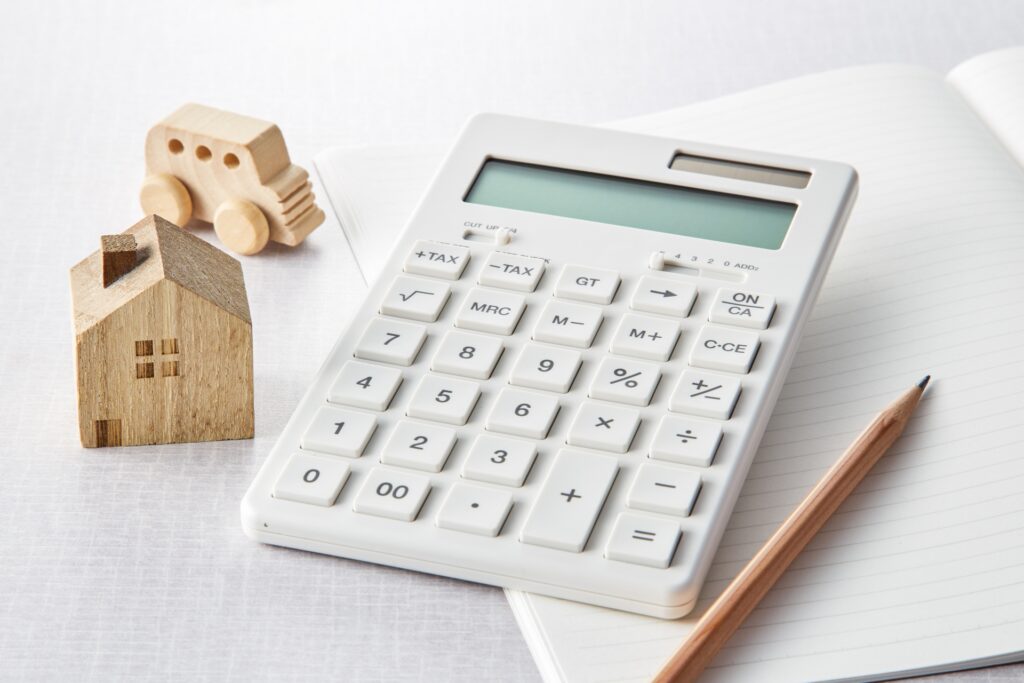
総務省の「令和5年住宅・土地統計調査住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果」によれば、空き家の増加は深刻な社会問題となっています。1998年には約576万戸だった空き家が、2023年には約900万戸まで増加しました。
<空き家数と空き家率の推移>
| 調査年 | 総住宅数(万戸) | 空き家数(万戸) | 空き家率(%) |
|---|---|---|---|
| 1998年 | 5,025 | 576 | 11.5 |
| 2003年 | 5,389 | 659 | 12.2 |
| 2008年 | 5,759 | 757 | 13.1 |
| 2013年 | 6,063 | 820 | 13.5 |
| 2018年 | 6,241 | 849 | 13.6 |
| 2023年 | 6,502 | 900 | 13.8 |
特に注目すべきは、地方圏での空き家率の高さです。和歌山県や徳島県では空き家率が21%を超え、山梨県でも20%を超える状況となっています。つまり、5軒に1軒が空き家という深刻な状態なのです。少子高齢化が進む日本では、この傾向はさらに加速すると予測されています。
賃貸住宅に限定して見ても、状況は厳しくなっています。賃貸住宅の空き家率は年々上昇し、2023年時点で約19%に達しており、賃貸住宅5戸のうち1戸近くが空き家という計算になります。
負動産化を防ぐための3つの出口戦略

【戦略①】早期売却という選択
相続した実家に誰も住む予定がないなら、早期売却が最も現実的な選択肢です。建物は時間とともに価値が下がり、売却が難しくなります。特に築30年を超えると建物の資産価値はほぼゼロとなり、土地の価格だけで取引されることが一般的です。
売却を検討する際のポイントは、複数の不動産会社に査定を依頼し、地域の相場を把握することです。また、空き家バンク(※自治体が運営する空き家情報の登録・紹介制度)を活用すれば、移住希望者とマッチングできる可能性もあります。
【戦略②】賃貸・活用で収益化
立地条件が良ければ、賃貸物件として活用する道もあります。最近では、古民家カフェやゲストハウス、シェアハウスなど、古い建物の特性を活かした事業も注目されています。
- 戸建て賃貸: リフォームして賃貸住宅として貸し出す
- 民泊・ゲストハウス: 観光地であれば宿泊施設として活用
- 地域コミュニティスペース: 自治体と連携して地域の交流拠点に
ただし、賃貸経営にはリスクも伴います。初期投資としてのリフォーム費用、入居者が見つからない空室リスク、建物の維持管理責任などを十分に検討する必要があります。
【戦略③】相続放棄という最終手段
どうしても活用も売却もできない場合、相続放棄(※相続人としての権利を放棄すること)という選択肢もあります。ただし、相続放棄は「すべての相続財産」を放棄することになるため、預貯金や他の不動産も含めて一切相続できなくなります。
相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。期限を過ぎると、原則として相続を承認したものとみなされてしまうので注意が必要です。
今から準備できること

親世代とのコミュニケーション
若い世代の皆さんにとって、相続はまだ遠い未来の話かもしれません。しかし、だからこそ今から準備することが大切です。まずは親や祖父母と実家の将来について話し合ってみましょう。
- 実家の資産価値はどのくらいか
- 将来誰が住む予定なのか
- 売却や活用の可能性はあるか
こうした会話を通じて、家族全員で将来の方向性を共有しておくことが、後々のトラブルを防ぐことにつながります。
不動産の基礎知識を身につける
将来に備えて、不動産に関する基本的な知識を身につけておくことも重要です。固定資産税の仕組み、不動産の評価方法、相続税の計算方法など、基礎的な知識があれば、いざという時に適切な判断ができます。
国土交通省の「不動産情報ライブラリ」では、不動産取引に関する様々な情報が公開されています。10代のうちから少しずつ学んでおくことで、将来の資産形成に役立つでしょう。
まとめ
空き家900万戸時代を迎えた日本では、実家の相続が「資産」ではなく「負債」となるケースが増えています。年間35万円から50万円の維持費、特定空き家に指定されるリスク、売却困難な物件の増加など、問題は深刻化しています。しかし、早期売却、賃貸活用、相続放棄など、適切な出口戦略を知っていれば、負動産化を防ぐことは可能です。
大切なのは、問題を先送りせず、早めに行動を起こすこと。そして若い世代の皆さんには、今から家族と将来について話し合い、不動産の基礎知識を身につけておくことをお勧めします。将来の資産形成において、実家をどう扱うかは重要な選択となるでしょう。今日から少しずつ、準備を始めてみませんか。