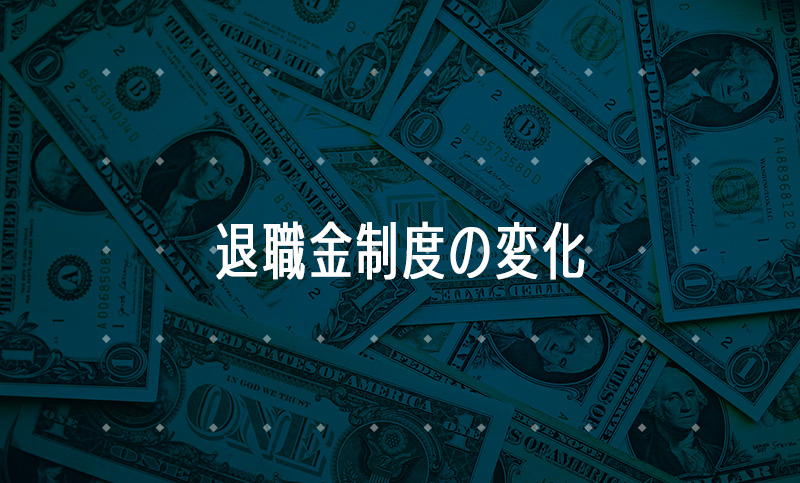戦後から続いてきた終身雇用制度が限界を迎え、多くの企業で雇用のあり方が見直されています。この変化は、退職金制度にも関わってきます。これまでの「退職一時金制度」から「確定拠出年金制度」への移行が進み、働く人々が自分で老後資金を準備する時代になってきました。
とくに今の学生や20代の方にとって、この変化は将来の生活に直結する大きな問題です。「会社が老後の面倒を見てくれる」という考え方が通用しなくなった今、早めに退職金制度の変化を理解し、適切な準備をする必要があります。
確定拠出年金が主流の時代に

日本の退職金制度は、長い間「退職一時金制度」が中心でした。しかし、企業の負担軽減や転職の増加などを背景に、多くの企業が確定拠出年金制度を取り入れるようになっています。
確定拠出年金制度を理解するうえで知っておきたいのが、拠出限度額の仕組みです。2024年12月の制度改正で、拠出限度額が次のように変わりました。
確定拠出年金の拠出限度額(2024年12月改正後)
| 制度・対象者 | 拠出限度額(月額) | 備考 |
|---|---|---|
| 企業型DC | 55,000円 | DB等の他制度掛金相当額を控除 |
| iDeCo(第1号被保険者) | 68,000円 | 自営業者等、国民年金基金等の額を控除 |
| iDeCo(第2号被保険者) ※企業年金等なし | 23,000円 | 公務員を除く |
| iDeCo(第2号被保険者) ※企業年金等あり | 20,000円 | 2024年12月に12,000円から引上げ |
| iDeCo(第3号被保険者) | 23,000円 | 専業主婦(主夫)等 |
この改正により、企業年金等がある場合のiDeCo拠出限度額が月額12,000円から20,000円に引き上げられました。これで、より多くの方が老後資金の準備を充実させられるようになったのです。この変化は、働く人々にとって次のような影響をもたらします。
- 会社任せではなく自分で運用
- 転職しても資産の移管が可能
- 金融リテラシーの向上が必要
これまで会社が退職金を管理・運用していましたが、今後は個人で運用することになります。なお、転職時に年金資産を新しい会社に移せるため、転職が当たり前の時代に適した仕組みです。ただし、投資の知識がないと老後資金に差が生まれるため、お金の勉強がより重要になります。
退職金格差の現実

退職金制度の変化と同時に、大きな問題となっているのが退職金格差です。厚生労働省の調査(2023年)によると、大学卒業者の勤続35年以上の退職金額には、企業の規模によって大きな差があります。
企業規模別退職金額(勤続20年以上・45歳以上の退職者平均)
| 従業員数 | 大学・大学院卒 | 高校卒 |
|---|---|---|
| 1,000人以上 | 2,007万円 | 1,899万円 |
| 300~999人 | 1,618万円 | 1,232万円 |
| 100~299人 | 1,295万円 | 985万円 |
| 30~99人 | 1,162万円 | 731万円 |
大企業と中小企業の間で、退職金額に最大約2.7倍の差があることが分かります。とくに高校卒の場合、従業員1,000人以上の企業と30~99人の企業では約1,200万円もの差が生じています。また、非正規雇用者の多くは退職金制度の対象外となっており、老後資金の準備を完全に個人に委ねられているのが現状です。
さらに気になるのが、働き方による格差です。非正規雇用の方の多くは退職金制度の対象外となっており、正社員との間には大きな老後資金格差が生まれています。
20代から始める老後の資産づくり

複利効果のすごさ
退職金格差や制度変更に対応するため、若い世代は早めの資産づくりが欠かせません。とくに大切なのが「複利効果」の活用です。
例えば、月3万円を年利5%で運用した場合を見てみましょう。
- 20歳から開始(40年間):約4,580万円
- 30歳から開始(30年間):約2,497万円
- 40歳から開始(20年間):約1,233万円
このように、始める時期が10年違うだけで、最終的な資産額には大きな差が生まれます。
使える資産づくりの制度
若い世代が活用できるおもな資産づくり制度を紹介します。
- 年間投資枠:40万円
- 投資期間:20年間
- 税制優遇:運用益が非課税
つみたてNISAは投資初心者にも使いやすく設計されており、月々数千円から始められます。
- 拠出限度額:職業により月額1.2万円~6.8万円
- 税制優遇:拠出時・運用時・受給時の三段階で優遇
- 60歳まで引き出し不可:老後資金をしっかり準備
iDeCoは税制優遇が手厚く、老後資金づくりには最適な制度です。
- 勤務先が制度を導入している場合に利用可能
- 企業からの拠出に加え、個人拠出(マッチング拠出)も可能
企業型確定拠出年金は、会社が掛金を出してくれるうえに自分でも追加拠出できる制度です。
転職時代の退職金戦略

転職が当たり前となった現代では、転職先に持ち運べる資産づくりが重要です。これまでの退職一時金制度は転職時にリセットされてしまいますが、確定拠出年金やNISA、iDeCoは転職先でも続けられます。
転職時代に適した資産づくり戦略の主なポイントは、以下のとおりです。
- 会社に頼らない制度を活用する
- 複数の制度を組み合わせる
- 早めのスタートを心がける
これらのポイントを実践することで、転職によるキャリアの変化に左右されない安定した資産形成が可能になります。iDeCoやつみたてNISAなどの個人で続けられる制度を中心に据え、リスクを分散させながら時間を味方につけた長期的な資産づくりを進めることが大切です。
まとめ
終身雇用制度の変化は、日本の働き方と老後準備のあり方を根本から変えました。企業が従業員の老後を保障してくれる時代は終わり、個人が自分で資産づくりを行う時代がやってきています。とくに今の学生や20代の方にとって、この変化は避けて通れない現実です。
しかし、早めに適切な準備を始めることで、豊かな老後を実現することも十分可能です。大切なのは、制度の変化をきちんと理解し、複利効果を最大限に活用できる若いうちから行動を始めることです。つみたてNISAやiDeCoなどの制度を上手に使い、転職時代に適した持ち運べる資産づくりを心がけましょう。
「老後の準備は定年が近くなってから」という考え方は、もう通用しません。新しい時代の退職金制度を理解し、今すぐ行動を始めることが、安心できる老後への第一歩となります。