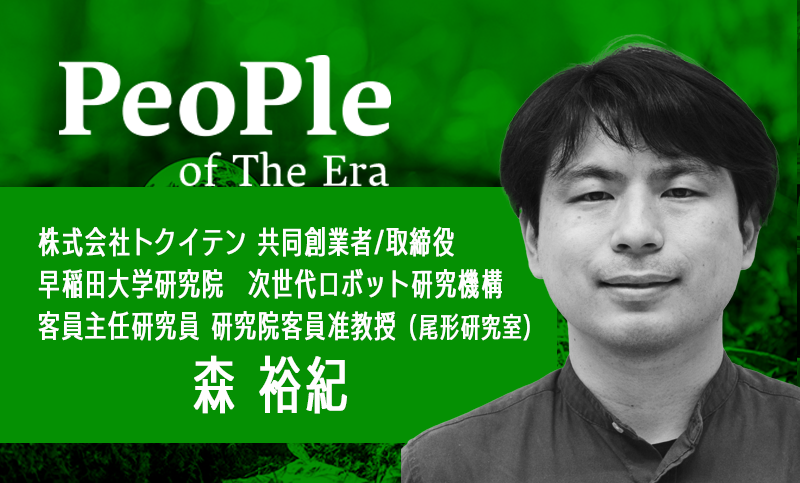インタビュー取材にご協力いただいた方
森 裕紀(もり ひろき)氏
株式会社トクイテン 共同創業者/取締役
早稲田大学研究院 次世代ロボット研究機構 客員主任研究員
研究院客員准教授(尾形研究室)
1981年愛知県生まれ。岐阜高専時代にロボコン全国準優勝を経験し、ロボット・人工知能・計算論的神経科学分野への道を歩む。豊橋技術科学大学で学士と修士を取得。東京大学で博士号取得後、大阪大学助教、フランス研究員を経て早稲田大学へ。胎児からの赤ちゃん研究を行う構成論的発達科学や深層学習によるロボット知能研究に従事。現在は株式会社トクイテンで有機農業の自動化に取り組み、兼業している早稲田大学では引き続き身体性知能に関する学術研究を行なっている。博士(情報理工学)。
「日本の農業は、このままで本当に大丈夫なのか?」
私たちの食卓を支える基幹的農業従事者※1の平均年齢は、今や70歳※2に迫っています。人手不足や高齢化、担い手不足といった課題が山積し、今後、食の安定供給そのものが揺らぐ可能性すらあります。
こうした中で期待されているのが「スマート農業」です。トクイテンの共同創業者であり、早稲田大学のロボット研究者でもある森裕紀氏は、「ロボコン」で培った情熱と、農業現場での経験から得た気づきをもとに、ロボットによる農業の革新に挑んでいます。本記事では、森氏が描く日本農業の未来に迫ります。
※1:基幹的農業従事者:自営業として主として農業を営む人
※2:2024年基幹的農業従事者平均年齢69.2歳(「令和6年度食料・農業・農村の動向令和6年度食料・農業・農村施策第217回国会(常会)提出」)
【トクイテン創業秘話】ロボコンが結んだ縁と農業への情熱
―― 森先生がロボットに取り組むことになったきっかけについて教えていただけますか?
森先生:私がロボットに取り組むことになったのは、岐阜高専時代に遡ります。トクイテンの共同創業者である豊吉隆一郎代表取締役は、高専時代の同級生でした。電気工学科(現電気情報工学科)のでチームを作ってNHKロボコンに出場し、2000年には全国準優勝を果たしています。この共通の経験が、後に「ロボットで何か事業をしたい」という共通の夢へとつながりました。
豊吉は、私と創業前に、フィンテック系の会社を起業し、クラウド請求書作成ソフト「Misoca(ミソカ)」の開発・運営を行っていました。このサービスは、フリーランスや小規模事業者向けに、従来手作業で行っていた請求書作成から送付までのプロセスをWeb上で完結させるという画期的なものでした。当時、会計ソフトのWebサービスがあまり存在しない中で、豊吉は「Misoca」を開発し、後に会計ソフト大手である弥生株式会社に売却することになります。この成功体験が、彼の次の挑戦への原動力となりました。
―― そこからトクイテン創業に至るまでの経緯についてお聞かせいただけますか?
森先生:私は大阪大学で助教として5年間働いた後、フランスに1年間滞在し、帰国後、早稲田大学で研究活動をしていたのですが、豊吉から「一緒に何かやろう」と誘いを受けました。当時、豊吉は弥生会計へのMisoca社売却後のロックアップ※3の期間中でしたが、それでも2人は将来の事業について話し合いを重ねました。そして、豊吉のロックアップが終わったのを機に、2人で本格的に事業をスタートさせました。
※3ロックアップ:企業の株式公開(IPO)やM&A(合併・買収)の際に、売り手の代表取締役などの実権者を一定期間、企業に残置させる契約。期間は3年ほどが目安となる。
―― あえてロボット技術を農業に応用することにしたのは、どういった背景からでしょうか?
森先生:農業を始めたのは、豊吉の個人的な経験が大きく影響しています。豊吉は弥生を退職後、友人の花卉(かき)農家を手伝ったのですが、彼のプログラミングとIoTの技術を組み合わせ、わずか数万円の費用で、DIYのノリでスマホから水やりができる遠隔監視システムを構築しました。水やりのため、ビニールハウスまで数時間かけて行かなければならなかった農家は、このシステムのおかげで旅行にも行けるようになり、心から喜んでいたそうです。この経験を通じ、豊吉は日本の農業が抱える技術が活用されない現状と、そこに潜在する技術による変革の大きな可能性を感じました。同時に、彼自身が子を持つ親として、次世代のために食料生産の基盤である農業を守り、発展させることの重要性を強く感じたと言います。その中で、持続可能な農業を進めるためどのようにしたら良いか2人で議論し、有機農業をロボットなどにより自動化していくスタートアップ「トクイテン」を共同創業しました。
日本農業のリアルとロボット導入の壁
―― 現在の日本の農業現場において、ロボット技術の導入はどの程度進んでいるとお考えですか? 導入が進んでいる分野、あるいは遅れている分野があれば教えてください
森先生:農業全体で考えるとロボット技術は全然導入されていません。近年、運搬用のロボットや、作業者が座って移動をモーターに任せるタイプの機械は登場していますが、まだまだ普及には至っていないのが現状です。一方で、米作のように伝統的に機械化が進んでいる分野では、自動運転の田植え機やコンバインが一部で導入され始めています。ジャガイモなどの固い作物の自動収穫機も存在しますが、これも完全自動化には至っていません。歴史的に100年以上前からトラクターが使われているように、「知能化」を伴わない「機械化」は徐々に進んできました。しかし、繊細な作業が必要な果菜類の収穫やその他の農作業に関しては、例えばトマトやナス、キュウリといった多くの作物で未だに手作業が主流です。
―― なぜ農業ではロボット技術の導入が進まないのでしょうか?
森先生:導入が進まない原因は3つです。1つ目は「農家にお金がない」という経済的な問題です。新しいロボット技術は高価で採算の問題があります。2つ目は農業従事者の高齢化です。日本の農業従事者の平均年齢は毎年1歳ずつ上昇し、今年は70歳に達するとされています。さらに、全農業従事者の70%程度が65歳以上であるというデータもあります。彼らに高額な設備投資を促しても、「10年後も農業をやっているか分からない」という切実な声が上がるのは当然のことです。農業従事者が導入へのモチベーションを持てない、あるいは持てない状況にあることが、ロボット化の大きな壁となっています。
3つ目は、まだちゃんとした製品が出てきていないという供給側の課題です。現在の農業ロボットはプロトタイプ段階のものが多く、実際に農家が手頃な価格で導入し、役立つと実感できる製品が少ないのが現状です。トマト分野においても、研究開発段階のものは多数存在しますが、人の繊細な作業をロボットが代替するレベルには至っていません。実際に導入されることで見つかる改善点も、普及が進まないために蓄積されにくいという悪循環があります。
―― 高価なロボットの導入障壁を克服するために、「ロボットのシェアリング」というアイデアも浮上しています
森先生:シェアリングは難しいですね。トマトのように、ある一定期間、ずっと取り続けなければならない作物の場合、収穫作業の日程が重なるため、同じ地域で複数の農家が同じロボットを共有することは現実的に困難です。シェアリングが有効な作物もあるかもしれませんが、切り札にはならないでしょう。
ロボットが変える農業とは? 生産性と労働環境の改善
―― では、ロボット技術は農業におけるどのような課題を解決できると考えていらっしゃいますか?
森先生:確かに先ほどの課題はありますが、ロボット技術が農業にもたらすメリットは計り知れません。ロボットが解決できる具体的な課題は、少人数で農業ができるようになる点です。これにより、深刻な人手不足が解消され、ひいては人件費の削減にもつながります。特に、収穫作業は多くの作物で最も大変な労働であり、労働集約的になりがちです。トマトやキュウリのように、収穫適期を逃すと品質低下や腐敗の恐れがある作物は、短期間で大量の収穫を行う必要があります。この作業をロボットが担うことで、人間は、より高度な作業に集中できるようになり、労働環境の改善にもつながるでしょう。
―― それ以外で、ロボットを導入するメリットはどのようなことでしょうか?
森先生:収穫量が増えると、それに比例して大変になるのが出荷作業です。例えば、出荷作業における「選果(せんか)」と「パッケージング」。選果とは、収穫した作物を品質によって選別する作業で、A品、B品、廃棄などに分けることです。現在、これも手作業で行われている部分が多いのですが、機械化や画像認識による自動選果、一定量をパックに詰めるパッケージング作業の自動化が進められています。
実際にトクイテンでも、出荷作業については、部分的な自動化を行いました。これにより、ベルトコンベアを導入するだけで効率が飛躍的に向上しました。大規模農場ではすでに電動式のパッケージング装置が導入されています。必ずしも見た目が「ロボット」と認識されるものだけでなく、AIによる画像認識を用いた選別など、目立たない形でも新しい技術が農業現場に導入されつつあります。こうした技術は、農業の生産性を向上させ、労働環境を改善する上で欠かせない存在となっていくでしょう。
トクイテンの挑戦、吸引式トマト収穫ロボットと持続可能な有機農業

―― 森先生が現在注目されている、あるいは開発に携わっていらっしゃる農業ロボット技術について、具体的な事例を交えて教えてください
森先生:現在開発に携わっているのは、ミニトマトを収穫するロボットです。このロボットの最大の特徴は、「空気で吸うことによってもぎ取る」という独特の収穫方式にあります。以前は100円ショップのトングを改造してトマトをつまみ、ひねって取る方法を試していましたが、収穫速度と成功率の課題に直面しました。そこで着目したのが吸引方式で、現在はこの技術に注力しています。開発は着実に進んでいて、すでに収穫システムそのものは実用段階に入っています。昨年の9月にトマトを植え付け、今年の6月末に収穫を終えたシーズンでは、80kg以上のトマトをロボットで収穫し、実際に出荷しました。ロボットが収穫したトマトについて、現状クレームは来ていないので、自信を持っています。



―― 今後の展望についてお聞かせください
森先生:現在の目標は、人間1人分の収穫量をロボット2台でまかなうことです。今年の1月には、1日で23.35kgのトマトをロボットで収穫するという記録を達成しました。現状のロボットはレール上を移動するタイプですが、今年中には、1台のロボットが農場内を巡回し、自動で収穫作業を行う完全自律型ロボットの実現をめざしています。トクイテンには経験豊富で新しいものづくりができる優秀なメンバーが集まっているので、先発組より開発速度が速いと思っています。
それに加えて、ロボットに限らず有機農業全体の自動化もめざしています。化石燃料に依存する化学肥料は、国際情勢によって価格が変動しやすく、日本の場合、100%輸入に頼っています。ウクライナ戦争のような国際紛争が起これば価格が3倍にも高騰し、農家の廃業につながりかねません。こうした外部要因に左右されないサステナブルな農業をめざし、微生物などを生かした有機農業をロボットで自動化しようとしています。これは、完全に環境をコントロールして自動化するわけではありません。農業の実情に合わせたロボットを開発し、同時にロボットの作業効率を最大化できるよう農場自体も最適化していくという、両面からのアプローチが特徴です。こうしたバランス感覚が、トクイテンの強みだと思っています。
「人間不要」の未来? ロボット研究者が描く農業の究極形と、若者への熱いメッセージ
―― 森先生が思い描く、高齢化・人口減少社会における「理想のロボット化農業」とはどのようなものでしょうか?
森先生:私が思い描く、高齢化・人口減少社会における理想のロボット化農業は、「完全無人化」です。つまり、ロボットが収穫から出荷まで全ての作業を自動で行い、人間の手がかからない農場をめざすものです。しかし、世の中には「人間がやらなければダメだ」という意見や、「農業は人を成長させる」といった考えを持つ人もいます。そうした意見も理解できますが、あくまでも私の理想は完全自動化です。
完全自動化に向けて、今後は、人とロボットが共存する段階を経て、最終的にはロボットが全ての作業を担う未来をめざしています。今はまだ全てロボット完了できるわけではなく、補完関係にありますが、それはあくまで「妥協」です。究極の目標は、ロボットが全て代替する未来にしたいと考えています。実際、我々の農場の周囲でも90代の地主の農地を80代の方が管理しているといった現状があり、持続可能ではありません。あくまで完全自動化を目指すことで、現実の農業の問題を解決できると思っています。
―― 最後に読者の方に向けてメッセージをお願いできますか?
森先生:私たちは難しいことにチャレンジしていますが、身につけた基礎的な知識や技術を現場に応用していく形で進めています。勉強せずに現場に来ても何もできませんし、逆に研究室の中で机上の空論ばかり行い、農業を知らずに技術開発しても、うまくいきません。ですから、様々な基礎技術を勉強し、自身で生み出せる力を身につけて、大学や大学院で学んでいってもらえれば、こういった場所でも活躍できると思います。
今日のロボット技術の劇的な進歩は、ディープラーニングなどAI技術の発展だけでなく、「発想」も関係しています。技術はどんどん進歩しますが、「それをどう使うか」「どのような技術が求められているか」を議論するのは、決して研究者や技術者だけに限られるべきではありません。もっと幅広い人たちが主体性を持って議論し、関わっていくことが必要です。そうしないと、社会に悪影響を与えるようなものが作られてしまう可能性があります。実際に、戦争に使われたり、有名人の声真似AIが詐欺に使われたりといった問題も起きています。ですから、ぜひいろいろな情報収集を行い、能動的にそういった議論の場に参加していくような気持ちで勉強し、実践していってもらいたいです。そして専門家とも議論していくことが必要です。そうした時に、負けないように、自分たちの未来を自分たちで切り拓いていけるように勉強していってほしいと思います。
森 裕紀先生のご紹介リンク:
ー researchmap:森 裕紀(Hiroki Mori)– マイポータル