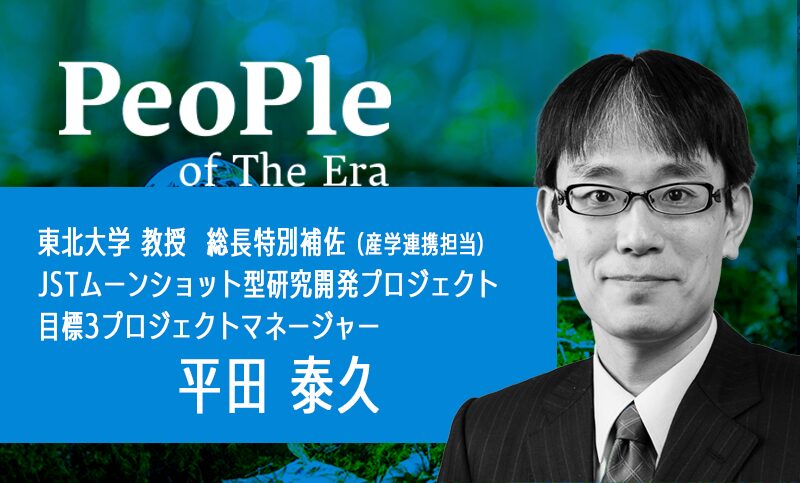インタビュー取材にご協力いただいた方
平田 泰久(ひらた やすひさ)氏
東北大学・教授 総長特別補佐(産学連携担当)
JSTムーンショット型研究開発プロジェクト
目標3プロジェクトマネージャー
1975年宮城県生まれ。東北大学工学部卒業。同大学院工学研究科 修士課程修了。博士(工学)。東北大学大学院工学研究科にて助手、助教授・准教授を経て、2016 年より現職。2020年に内閣府ムーンショット型研究開発制度 目標3プロジェクトマネージャーに就任。
2005年日本機械学会賞(論文)、2005年日本ロボット学会論文賞、2006年ファナックFAロボット財団論文賞、2014年科学技術分野文部科学大臣表彰若手科学者賞、2016年Advanced Robotics Best Paper Award、2020年永守賞等受賞。
監修書に『絵でわかるロボットのしくみ』(瀬戸文美著)、共著書に『新版ロボット工学ハンドブック』など。
「ロボットは人の敵ではない」。そう語るのは、東北大学でAIロボットによる在宅ケアの研究を牽引する平田泰久先生です。鉄腕アトムのような人型ロボットのイメージが先行しがちな「ロボット」の概念を再定義し、「ニンバス」という新たな言葉で、目指す未来を提示します。果たして、人が「できる」を実感し、自立した生活を送るためのAIロボットとは? そして、その社会実装への道のりは、私たちに何をもたらすのでしょうか。平田先生にお話を伺いました。
ブレーキだけで未来を変える? 在宅ケアに革命を起こすロボット技術
―― まず、平田先生がAIロボットによる在宅ケアの研究に着手されたきっかけや、その必要性を感じられた具体的なエピソードがあれば教えてください
平田先生:大学時代は、複数のロボットが協力して重い物を運ぶパワーアシスト技術を研究していました。人が少し力を加えるだけでロボットがそれを増幅し、楽に運べる仕組みです。当時は社会課題の解決というより、「人の役に立つロボットを作りたい」という漠然とした思いが動機でした。研究を続けるうちに、高齢者用の歩行器をロボット化すれば、安全に、より楽に歩けるのではないかと気づき、現在の研究につながっていきました。
―― 先生は普通のロボットのようにモーターを使っていません。理由を教えていただけますか?
平田先生:多くのロボットはモーターで動きを制御しますが、私はあえてモーターを使わず、ブレーキだけで制御する歩行器を開発しました。モーターは誤作動すると意図せず回転する(ロボットが勝手に走り出す)リスクがありますが、ブレーキ制御ならロボットが止まるだけなので安全性が高まります。また、パワーアシストは「引っ張られている」感覚がありますが、ブレーキ制御なら「自分で押して歩いている」という実感が得られます。高齢者のその体験が「自分で歩ける」という自信につながることがわかり、やる気を引き出すロボットの可能性を感じたのです。
ヒューマノイドから生活支援まで、AIロボットの進化と現実のギャップ
―― そもそもロボットの定義とは?
平田先生:ロボットの定義は「センサー・アクチュエーター・コントローラーの三要素を持つ機械」です。この定義に基づけば、洗濯機や自動運転車もロボットに含まれ、すでに多くのロボットが私たちの生活に溶け込んでいます。一部の研究者は人型ロボットのヒューマノイドやロボットアームがついた産業用ロボットの開発を行っていますが、多くの研究者はあまりそこにこだわっていません。先ほど申し上げた3要素があれば様々な支援機器が開発できると思っています。
―― 現在AIロボットの進化がめざましいと言われていますが、実際、どの程度の進化をしているのでしょうか?
平田先生:ホンダの「ASIMO(アシモ)」やトヨタの「パートナーロボット」、ソニーの「
QRIO(キュリオ)」のようなヒューマノイドロボットは、昔から数式モデルに基づいて制御されてきました。しかし、段差の誤差や予想外の地形に弱く、転倒しやすいという課題があったのです。近年はAIの進化により、仮想環境での学習を通じて安定した歩行を習得し、マラソン完走やボクシングなど高度な動作も可能になっています。
しかし、シミュレーターの中では、料理のように素材の物理変化を伴う作業や、人間の複雑な反応を理解する作業などについては、AIの限界は顕著です。人間の行動や感情をシミュレーションするのは依然として困難で、介護の現場で「人のそばで働く」レベルにはまだ達していません。
「自分でできる」を支えるロボット――控えめに寄り添う未来の在宅介護
―― 現在、日本が抱える社会問題の中で、AIロボット技術が特に貢献できる分野は何でしょうか?
平田先生:私は、ヒューマノイドロボットが家族の代わりに在宅介護を全面的に担う未来には懐疑的です。技術的な難しさに加え、「利用者の主体性を尊重する介護」という私の理念に反するからです。理想の在宅ケアとは、高齢者が「まだ自分でできる」と感じ、自立した生活を続けられること。そのためには、ロボットがすべてを代行するのではなく、利用者の力を引き出し、不足を「さりげなく補う」存在であるべきです。そうした支援には、利用者の状態を正確に見極め、本当に必要なときに目立たずサポートする技術が欠かせません。私は、そんな控えめで的確な支援を行うロボットの制御技術を目指しています。
―― 「さりげなく補う」ロボットとは、具体的にどのようなものでしょうか?
平田先生:私は、ロボットを「賢い家電」や「スマートな補助具」として捉えています。たとえば、ベッドの高さが自動調整されて立ち上がりやすくなったり、歩行器が動きを先読みしてサポートしたりするようなイメージです。こうした機能が連携することで、利用者は支援を意識せず、自分の力で日常生活を送れるようになります。そうしたロボットは、硬さの変わるズボンで立ち上がりが楽になるなど、自然に生活に溶け込む工夫が重要です。「ロボットに助けられている」ではなく「自分でできている」と感じることで、QOL向上につながるはずです。すでに述べたように、ベッドやトイレ、歩行器といった身近な道具がロボットとして連携すれば、在宅での自立支援はさらに進むと考えています。
「立って動く、踊って笑う」——ロボットが変える介護の未来
―― 現在、特に注力されているAIロボットの具体的な開発プロジェクトについて教えていただけますか?
平田先生:現在は「モビリティ」の開発に力を入れており、立ったまま移動できるロボットの研究を進めています。セグウェイ※1のような移動体を参考にしつつ、高齢者でも安心して使えるよう、転倒しにくい安全設計が特徴です。介護施設では転倒リスクを避けるため、多くの利用者が車椅子を使っていますが、長時間座ることで姿勢の崩れや、目線が合わず会話しにくいといった課題もあります。そこで、立位を保てる人がこのロボットを使えば、目線を高く保ちながら自分でトイレに行ったり、会話を楽しんだり、買い物や美術館へ出かけることも可能になります。これは、自立と生活の質の大きな向上につながると考えています。
セグウェイ※1:セルフバランステクノロジーを採用した搭乗型モビリティロボット
―― 「モビリティ」を導入することで、他にどのような効果があるでしょうか?
平田先生:このロボットは、体の傾きで操作できる設計で、フィギュアスケーターのように滑らかに移動してダンスを踊ることも可能です。もともとは技術的な挑戦として始めた機能ですが、ダンスの専門家からは新しい表現手段として、リハビリ関係者からは「笑顔が増える」「心理的にも良い影響がある」といった声が寄せられています。現在では、介護施設での生活を前向きに楽しむ手段として注目され、「みんなでちょっと踊ってみよう」といった軽い運動にも活用することが期待されています。ロボットが補助にとどまらず、生活に楽しさや活力をもたらす存在として発展する可能性に期待しています。
介護現場のニーズを研究開発に反映する「リビングラボ」
―― 介護現場のニーズを研究開発にどのように反映させていますか?具体的な取り組みがあれば教えてください
平田先生:私たちは現在、「リビングラボ※2」を運営しています。リビングラボでは、開発段階から介護現場の専門家と研究者が密に連携し、「共創」を通じて開発を進めます。これにより、「こんなロボットを作ったけれど、これは使えるか?」と問いかけ、すぐに「これは使えない」「この使い方なら可能性がある」「ここを改良すればもっと良くなる」といった具体的なフィードバックが得られます。この迅速かつ建設的なフィードバックサイクルにより、研究開発の効率が飛躍的に向上し、真に現場で役立つロボットの開発につながっています。現場の専門家からの厳しい意見も、研究者にとっては新たな視点や改善点を発見するための貴重な情報源となっています。
リビングラボは、厚生労働省の予算で運営されており、企業からの相談を積極的に受け付けています。ひいては、大学の研究室だけでなく、多くの企業が現場のニーズに基づいた開発を進めることが可能になっています。また、私たちが進めているムーンショットプロジェクト※3で開発しているロボットの評価も行っています。
※2リビングラボ:実際の生活空間を再現し、利用者参加の下で新しい技術やサービスの開発を行うなど、介護現場のニーズを踏まえた介護ロボットの開発を促進するための機関
※3ムーンショットプロジェクト:多くの人々を魅了するような斬新かつ挑戦的な目標を掲げ、国内外からトップ研究者の英知を結集し、関係府省庁が一体となって集中・重点的に挑戦的な研究開発を推進するプロジェクト
ロボット普及の壁、お金と「新しいもの嫌い」
―― AIロボットの在宅ケアへの本格的な導入に向けて、現在最も大きな課題は何だとお考えですか?
平田先生:社会実装には主に二つの大きな課題があります。一つは「価格」の問題です。どんなに優れた機能を持つロボットでも、導入費用が高ければ、一般家庭に普及させることは困難です。例えば、特定の介護機能に特化したロボットが高額であれば、その投資に見合う価値を見出すのは難しいでしょう。また、利用者のニーズは一人ひとり異なるため、それぞれの状況に合わせた柔軟な価格設定や機能のカスタマイズが求められますが、これは製造コストに直結する課題です。
そしてもう一つは、「日本人のマインド」、特に新しいものに対する保守的な傾向です。日本社会には依然としてFAXの使用が根強く残っていますし、ChatGPTのような便利なAIツールですら「怖いから……」という理由で敬遠されるケースがあります。介護ロボットについても、たとえ生活が便利になると分かっていても、「今困っていないから」「慣れないものは不安」といった理由で、新しい技術の導入をためらう心理が働く可能性があります。
―― そうした課題を解決するためにはどのような取り組みが必要でしょうか?
平田先生:これらの課題は、技術的な進化だけでは解決できない、社会や人々の意識に根ざした問題です。ムーンショットプロジェクトのような未来を見据えた研究は、数十年先の社会実装を視野に入れているため、現状で商品化されていないものも多いです。そのため、技術者だけでなく、倫理学者、法学者、社会学者などとの連携も行っており、新しい技術が社会にどのように影響するかを議論しています。また、今後は、これらの先進的な技術を、より安価で、現在の生活にスムーズに溶け込むような形で社会実装していくための取り組みが求められています。企業との連携や、大学発ベンチャーの設立なども、その有効な手段となるでしょう。
未来への一歩、ロボットと拓く「できる」社会
―― 今後、AIロボットによる在宅ケアの研究において、特にどのような分野に力を入れていきたいとお考えですか?
平田先生:私たちが目指しているのは、単なるモビリティ支援ではなく、「自分はまだできる」と思えるような環境を作ることです。年齢や障害によって「できなくなった」と感じることが増えるなかで、ロボットの力によって「できることが増えている」と本人が実感できるような支援を提供したいと考えています。そのためには、一人ひとりの残存能力を活かしつつ、本当に必要な場面で、過不足なく支援することが重要です。最終的には「自分でできた!」と感じられるような体験を提供することが、最も価値のある支援になるのではないでしょうか。こうした支援を実現するためには、「主観の変化」――つまり、利用者自身の気持ちや認識をどう変えていくかが大きなポイントになります。ただ身体を助けるのではなく、「自分でやっている」と思えるような支援であることが求められます。
―― ロボットに対するイメージの固定概念もあります。
平田先生:ロボットという言葉には、いまだに多くの誤解があると感じています。多くの人はロボットと聞くと、SFに出てくるような人型ロボットを想像しがちです。しかし、私たちの考えるロボットはもっと多様です。例えば、トイレの支援装置や、日常の服のように見えるアシスト機器も、その機能からすれば立派なロボットです。こうした誤解を解消するため、私は最近「ロボット」ではなくムーンショットプロジェクトで提案した「ニンバス※4」という言葉を使うようにしています。「ロボット」という言葉には「人の仕事を奪う存在」というネガティブな印象がつきまとうこともあり、介護現場で「職員がいらなくなるのでは」といった不安を生むことがあります。しかし、ロボットは本来、人を支える存在であり、敵ではありません。この認識を広めるためには、新しい呼び方や概念が必要だと考えています。
※4ニンバス:ニンバスには「光の雲」という意味があり、人の周りに雲のように違和感なく存在し、雲のように自由に形を変え、筋斗雲のようにその人の能力を拡張してくれる存在となる新しいロボットのコンセプト
さらに、AIとロボットの混同も課題です。AIの定義やロボットの概念についても、研究者と一般の人々の間には大きな隔たりがあります。私たちが「アクチュエーター、センサー、コントローラーの三つが揃えばロボット」と考える一方で、一般の方は人型を想像することがほとんどです。このような言葉の解釈のズレは、技術開発の意図が正しく伝わらず、誤解を生む原因となります。だからこそ、ロボットやAIの研究者がどのような目的で技術を開発しているのかを、より丁寧に、そして分かりやすく伝えていくことが、今後の社会でますます重要になると感じています。
―― 最後に読者の方に向けてメッセージをお願いできますか?
平田先生:ロボット研究は、単に技術の進歩や性能向上を目指すものではありません。重要なのは、ロボットが導入されたことで社会がどう変わるのか、その未来像を多くの人と一緒に考えていくことです。技術者だけではなく、介護や工場など現場のニーズを理解している人、心理学・法律・倫理・社会学といった文系分野の専門家とも協力しながら研究を進める必要があります。例えば「ロボットが人を励ますためにあえて少し騙すような言動をすることが許されるのか」といった倫理的な問題も議論しなければなりません。もともとロボット開発は、機械、電気、情報といった学際的な知識が求められてきましたが、今ではさらに幅広い分野との協働が不可欠になっています。
未来のロボット社会を形作るには、幅広い知見を持った人たちが関わることが重要です。だからこそ、特にこれから研究の世界に入る若い世代には、「多様な人と協力しながら社会に役立つロボットをつくっていく」という感覚を持ってもらいたいと思っています。
平田 泰久先生のご紹介リンク:
– 平田 泰久 | 東北大学 研究者紹介