石破茂総理が「選挙公約は必ずしも実現できるものではない」と発言し、波紋を広げています。この発言は多くの国民に「そもそも実現する気がないのでは?」という疑念を抱かせました。
しかし、これは日本の政治における一つの現実でもあります。選挙の際に掲げられる華やかな公約と、実際の政策実現の間には常に大きな溝があります。なぜ公約は実現されないのか、あるいはどのような公約が実現されやすいのか。過去の事例を振り返りながら見ていきましょう。
実現された公約と実現されなかった公約

実現された公約
過去に実現された選挙公約には、以下のようなものがあります。
| 実現された公約 | 実現時期 | 概要 |
|---|---|---|
| 高速道路の一部無料化 | 2010年~2011年 | 民主党政権下で高速道路の一部区間が無料化されたが、2011年の東日本大震災によって中止 |
| 子ども手当ての創設 | 2010年4月~2011年9月 | 民主党政権下で実現し、その後自民党政権下で児童手当として継続 |
| 消費税増税 | ・2014年4月 ・2019年10月 | 2014年4月に5%から8%へ、2019年10月に8%から10%へ引き上げ |
| マイナンバー制度の導入 | 2016年1月 | 2016年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーの利用が開始 |
実現された公約の多くは、具体的な制度設計がすでに進んでいたものや、官僚機構が推進していたものが多いという特徴があります。また、財源の裏付けが明確だったり、国際的な潮流に沿ったものであったりする傾向も見られるのではないでしょうか。
実現されなかった公約
一方で、以下のような実現されなかった公約も数多く存在します。
| 実現されなかった公約 | 検討時期 | 概要 |
|---|---|---|
| 「政治主導」の実現 | 2009年~2012年 | 民主党政権下で「官僚主導体制の打破」として掲げられたが、政策決定プロセスの問題や官僚との対立により失敗 |
| 道州制の導入 | 2000年代~現在 | 都道府県に代わる広域行政単位の創設が複数の政権で検討されたが実現していない多くの課題があり実現していない |
| 憲法改正 | 1990年代~現在 | 自民党が掲げ続けているが、国会発議に必要な3分の2以上の賛成が得られず実現していない |
| 原発ゼロ | 2011年~現在 | 東日本大震災後、民主党政権下で検討されたが、使用済み核燃料の扱いなど多くの課題があり実現していない |
実現されなかった公約の多くは、既存の利益構造を大きく変えるものや官僚機構の抵抗が強いものが目立ちます。また、国民全体の合意が難しいテーマや、実現のためのロードマップが明確でないものも多く含まれているといえるでしょう。
公約が実現されない要因

政権与党内の力関係
選挙公約が実現されない背景には、まず政権与党内の複雑な力関係があります。特に自民党のような大政党では、党内に様々な派閥や利益団体との結びつきがあり、一枚岩ではありません。
たとえば、農業改革や規制緩和などの公約は、党内の農林族議員や関連業界との関係から当初の公約通りに進まないことが少なくありません。また、連立政権の場合は、連立パートナーとの政策調整も必要となり、さらに複雑化します。
官僚機構の影響力
日本の政治システムでは、政策立案や実施において官僚機構が大きな影響力を持っています。2009年の民主党政権は「脱官僚依存」を掲げましたが、実際には官僚機構との対立が政権運営の障害となりました。
官僚機構は制度や予算の継続性を重視する傾向があり、大きな変革を伴う公約は実現のハードルが高くなります。また、互いの専門知識や情報が噛み合っていないこともあり、政治家が官僚の提案を覆すことは簡単ではありません。
外部環境の変化
選挙時に掲げた公約も、国際情勢や経済環境の変化によって実現が難しくなることがあります。たとえば、2011年の東日本大震災は当時の政権の政策優先順位を大きく変えました。
また、2008年のリーマンショックや2020年の新型コロナウイルス感染症の流行なども、それまでの政策方針の転換を余儀なくされた事例です。
こうした予測困難な外部環境の変化は、公約実現の大きな障壁となります。
財政的な制約
多くの魅力的な公約を実現するためには、大きな財政支出を必要とします。しかし、日本の厳しい財政状況のなかでは、新たな支出を伴う政策の実現は難しいかもしれません。
- 日本の政府債務残高:GDP比約260%(2023年時点)
- 税収:約60兆円程度
- 社会保障費:年々増加傾向
このような状況下では、財源の裏付けがない公約は実現が難しくなります。また、財政再建と景気促進のバランスも常に政策決定の難しさを増しています。
政治に賢く参加するために必要なこと
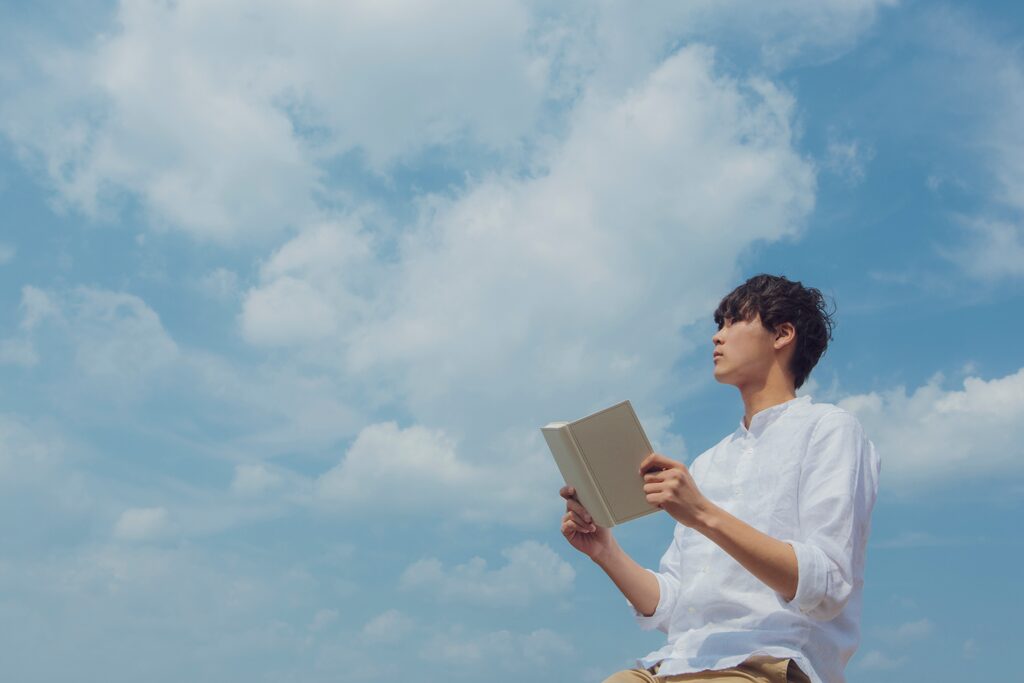
公約の実現度を見極める視点
選挙公約を評価する際には以下のような点に注目すると、その実現度をある程度見極められます。
- 具体性:抽象的な理念ではなく、具体的な施策や数値目標が示されているか
- 財源:必要な財源とその調達方法が明示されているか
- 実施主体:誰がどのように実行するのか、実施体制が明確か
- タイムライン:いつまでに実現するのか、工程表が示されているか
これらの要素が明確な公約ほど、実現度は高いと考えられます。逆に「〜を目指します」「〜を検討します」といった曖昧な表現が多用されている公約は、実現への本気度を疑ってみたほうがよいかもしれません。
政治家の過去の実績を評価
選挙公約の信頼性を判断するうえで、その政治家や政党の過去の実績を検証することも重要です。過去に掲げた公約をどの程度実現してきたか、実現できなかった場合にはその理由を詳しく説明しているかなどを確認することで、新たな公約の信頼性を測りやすくなります。
「言うは易く行うは難し」という言葉がありますが、政治の世界ではこれが顕著に表れます。過去の実績を踏まえて、現実的な視点で公約を評価する姿勢が求められるでしょう。
メディアリテラシーの重要性
選挙期間中は、各政党や候補者の公約がさまざまなメディアを通じて報じられます。しかし、その報道には偏りがあることも少なくありません。有権者としては、複数の情報源から情報を得て慎重に検討すべきでしょう。
特に近年はSNSなどを通じた情報拡散も活発で、誤った情報に惑わされるリスクも高まっています。公約の内容を自分自身で確認し、それを実現できる能性や社会的影響をさまざまな角度から見ることが、政治参加への第一歩となります。
まとめ
選挙公約は政治家と有権者を結ぶ約束といえますが、その実現にはさまざまな障壁があることも事実です。有権者としては公約を実現できる可能性を見極める目を持ちつつ、同時に政治家に対して公約実現への強い期待を示し続けなければなりません。
「政治は妥協の芸術」といわれることもありますが、その妥協の線をどこに引くかは最終的に有権者の判断にかかっています。選挙の際には華やかな公約に目を奪われがちですが、実現できる可能性や優先順位を見極めて投票行動に反映させることが、民主主義社会における有権者の責任といえるでしょう。
公約を「単なる選挙のための飾り」と諦めるのではなく政治家との対話の出発点として捉え、その実現に向けて建設的な圧力をかけ続けることが、よりより政治を実現する鍵となるのです。

