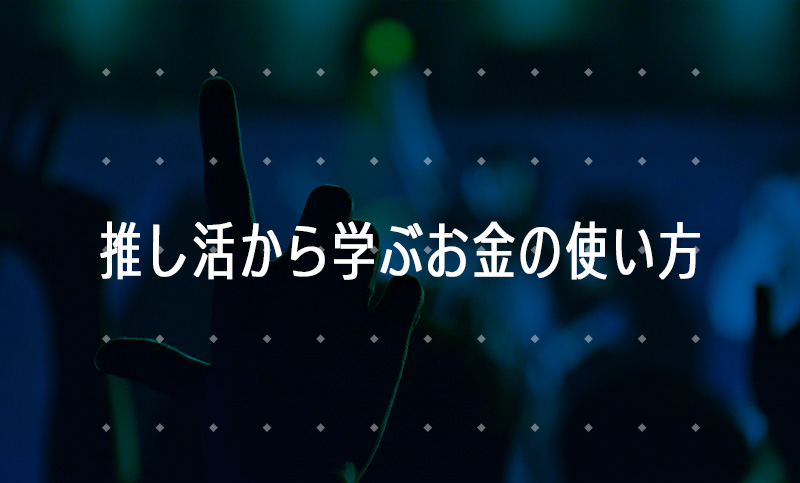最近、Z世代の間で「推し活」という言葉をよく耳にするようになりました。アイドルやアニメキャラクター、VTuberなどを応援する活動が、今や大きな経済圏を作り上げています。推し活総研の調査によると、2025年の推し活市場規模は3.5兆円にも達しているのです。
一見すると趣味の範囲に思える推し活ですが、実は投資の世界と共通する面白い仕組みがたくさん隠れています。推しへの気持ちと経済的な判断のバランス、ファン同士のコミュニティから得られる情報、限られた予算をうまく配分する技術など、推し活で自然と身についているスキルは、将来の投資にも十分活かせるものばかりです。今回は、推し活の経済的な仕組みを通じて、Z世代らしい投資の考え方を一緒に探ってみましょう。
推し活に学ぶ価値の見極め方

推し活をしていると、グッズを買ったりイベントに参加したりする時に、自然と「これは本当に価値があるかな?」と考えることがありませんか。この判断プロセスは、実は投資における「価値評価」の考え方とよく似ています。
推し活では、単純に「安いから買う」「高いから諦める」という判断だけではなく、その商品やイベントから得られる満足感や推しを応援できる喜びも含めて総合的に考えます。推し活での例を、投資での考え方に当てはめてみましょう。
| 考える要素 | 推し活での例 | 投資での似ている考え方 |
|---|---|---|
| 気持ちの満足度 | 推しを応援できる嬉しさ | 社会貢献を重視するESG投資 |
| レア度 | 限定グッズの特別感 | 将来性の高い成長株への期待 |
| 仲間との共有 | ファン同士で話題にできる | 注目テーマへの投資トレンド |
| 将来の価値 | プレミアがつく可能性 | 長期投資での資産成長 |
これらの価値判断は、株式投資で企業を評価するときの考え方と似ています。投資家も会社の業績だけでなく、将来性や社会への貢献度を総合的に見て投資先を決めているのです。
ファンコミュニティが作る経済効果

推し活の世界では、ファン同士のコミュニティが大きな経済効果を生み出しています。これは、投資の世界でも注目されている「ESG投資」や「テーマ投資」の仕組みと共通する部分があります。
ESG投資:環境・社会・企業統治を大切にする投資方法
テーマ投資:特定の分野やトレンドに注目した投資戦略
ファンコミュニティの経済力は、数字で見ても本当に大きなものです。株式会社CDGと株式会社Oshicocoが2025年1月16日~23日で23,069人に実施した「第2回 推し活実態アンケート調査結果」によると、推し活の市場規模は以下の結果となっています。
- 市場規模:3.5兆円
- 推し活人口:1,384万人
- 推し活人口の割合:16.7%
※出典:CDG「推し活人口は1384万人、市場規模は3兆5千億円に! 第2回 推し活実態アンケート調査結果を公式noteで公開。」
株式会社矢野経済研究所が調査した「オタク」市場の規模も見てみましょう。
| 年度 | 市場規模(億円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2020年度 | 6,730 | – |
| 2021年度 | 7,170 | 6.5% |
| 2022年度 | 8,330 | 16.2% |
| 2023年度 | 9,740 | 16.9% |
| 2024年度 | 10,090 | 3.6% |
この2つの市場規模が示しているとおり、推し活市場の規模は大きいことがわかります。
推し活予算術から学ぶお金の配分テクニック

推し活を長く楽しむためには、限られた収入のなかで何にどのくらい使うかを考える必要があります。この予算管理のスキルは、投資における「ポートフォリオ管理」の基本的な考え方と共通しています。
ポートフォリオ管理:リスクとリターンを考えながら資産を配分する方法
推し活ファンの実際の支出パターン
推し活の消費行動は「好きだから買う」という衝動的なものだけではありません。多くのファンが無意識のうちに、限られた予算のなかで最大限の満足を得るための判断を行っています。
- 体験重視の消費:ライブやイベントなど、推しと直接的につながれる体験にお金をかける
- 予算の見える化:月初に無理のない上限額を決め、イベント費は積立方式で準備する
- 優先順位の明確化:「物より経験」を重視し、見栄のための消費は控える
推し活から学ぶ資金管理の原則
推し活ファンが実践している予算管理には、投資の世界でも重要とされる原則が含まれています。推し活ファンの行動を、投資の原則に当てはめた例を見てみましょう。
推し活ファンは、グッズ購入費やイベント参加費、遠征費などの予算を目的別に管理しています。これは投資における「目的別投資」の考え方と共通しています。
「推し活破産」という言葉があるように、多くのファンが支出の上限を意識的に設定しています。これは投資における「リスク許容度」の設定と同じ発想です。
真のファンほど一時的な衝動ではなく、長期間にわたって推しを応援しつづけることを前提に予算を組んでいます。これは投資における「長期投資」の考え方に通じます。
現代のかしこい推し活術
現代の推し活では、必ずしも高額な出費が必要ではありません。以下のような、コストを押さえた推し活方法もあります。
- 公式YouTubeや無料配信でコンテンツを楽しむ
- 100均素材を使った推しグッズのDIY
- SNSでのファン同士の情報交換による効率的な情報収集
これらの工夫は、投資における「コスト意識」や「情報収集力」の重要性を表しているのではないでしょうか。
エンタメ株投資の魅力と可能性

推し活に夢中なZ世代にとって、エンターテインメント関連の企業に投資することは、自分の興味と資産運用を結びつける素晴らしい機会になります。矢野経済研究所の調査によると、オタク関連市場は2020年度から2024年度の5年間で約50%も成長しており、長期的な成長が期待できる分野です。
| 分野 | 2023年度 | 2024年度 ※当時の予測値 | 成長率 |
|---|---|---|---|
| アニメ | 345億円 | 350億円 | 1.4% |
| アイドル | 190億円 | 205億円 | 7.9% |
| 同人誌 | 128億円 | 134億円 | 4.7% |
| プラモデル | 60億円 | 63億円 | 5.0% |
| 2.5次元ミュージカル | 50億円 | 50億円 | 0.0% |
| フィギュア | 48億円 | 45億円 | -6.3% |
| 音声合成 | 21億円 | 26億円 | 23.8% |
なかでも「音声合成」市場は、2024年度に前年比23.8%増と最も高い成長を記録しています。これは「初音ミク」などのバーチャルシンガーの人気拡大や、動画配信での実況・解説動画の需要増加が背景にあります。投資先として注目したい企業の種類を見てみましょう。
- コンテンツを作る会社(アニメ制作、ゲーム開発など)
- 配信プラットフォームを運営する会社(動画サービス、SNS運営など)
- 関連サービスを提供する会社(イベント運営、グッズ製造など)
これらの企業への投資を考えるときは売上や利益などの数字だけでなく、ファンコミュニティの盛り上がりやコンテンツの人気度も大切な判断材料になります。推し活の経験があるZ世代なら、こうした空気感を読み取るのが得意な方も多いのではないでしょうか。そのため、推し活の経験は投資判断でも有利になる可能性があります。
まとめ
推し活の世界から学べる投資の考え方は、従来のお金の理論に新しい風を吹き込んでくれます。気持ちと数字のバランスを取ること、コミュニティの力を活用した情報収集、計画的なお金の配分など、推し活で自然と身についているスキルは投資にも十分応用できます。
実際に推し活市場は3.5兆円規模まで成長し、オタク関連市場も5年間で50%の成長を遂げるなど、その経済効果は数字でも証明されています。とくにZ世代にとって自分の興味や価値観と投資を結びつけることで、より楽しく継続的な資産づくりができるようになるでしょう。
推し活を通じて培った経済感覚を、将来の投資に活かしてみませんか。きっと、数字だけでは見えない投資の新しい魅力が発見できるはずです。